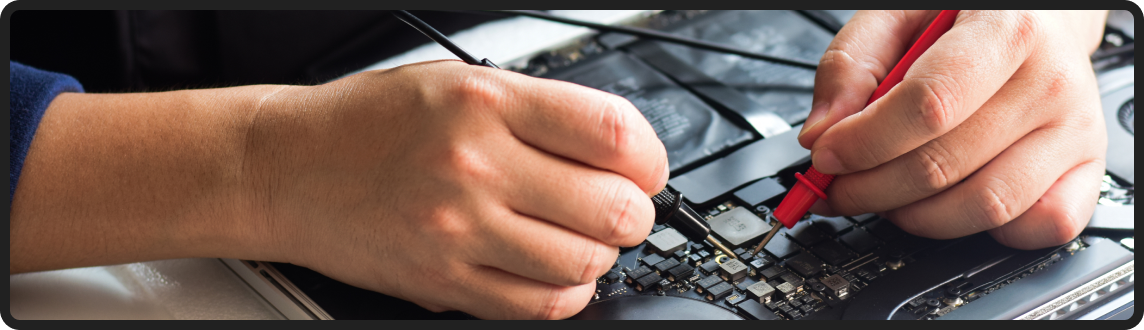パソコンがメーカーのロゴから進まない場合の原因と対処法【徹底解説】

Contents
パソコンがメーカーのロゴから進まない場合の原因と対処法【徹底解説】
パソコンの電源を入れたとき、メーカーのロゴ画面から先に進まないと非常に不安になりますよね。普段通りに使えるはずのPCが起動途中で止まってしまうと、仕事やプライベートの作業ができず困ってしまいます。
このような状況では「大切なデータは大丈夫?」「故障してしまったの?」と焦ってしまうものです。
しかし慌てる前に、落ち着いていくつかの対処法を試すことで、自力で問題を解決できる場合があります。
本記事では、パソコンがメーカーのロゴから進まない原因とその解決策について詳しく解説します。
まず考えられる原因を整理し、その後ソフトウェア・ハードウェア別の対処方法を紹介します。
メーカーのロゴから先に進まない原因
起動時にPCがメーカー(製造元)のロゴ画面で止まってしまう現象には、さまざまな原因が考えられます。
原因は大きく分けてソフトウェア面とハードウェア面のトラブルに分類できます。
ソフトウェア的な原因
- Windowsの更新失敗:
Windowsアップデートの最中や直後に不具合が起こり、システムが正常に起動できなくなることがあります。
特にアップデート途中で強制終了してしまった場合、OSのファイルが破損してロゴから進まない原因になります。 - ブートエラー・OS破損:
起動に必要なブートローダーやシステムファイルが壊れていると、メーカーのロゴ表示以降にOSを読み込めず止まってしまいます。
誤って重要なシステムファイルを削除したり、ウイルス感染によりOSが損傷した場合にも発生します。 - BIOS設定のミス:
BIOS(基本入力出力システム)の設定が不適切だと正しいドライブから起動できず、先に進めないことがあります。
たとえばブート順序が誤って変更され、OSの入っていないデバイスを起動しようとしているケースです。 - 周辺機器や増設デバイスの影響:
外付けHDDやUSBメモリなどの周辺機器が接続された状態で起動すると、それをブートデバイスと勘違いして起動が止まる場合があります。
また増設したメモリやグラフィックボードとの相性問題で起動が妨げられることもあります。
ハードウェア的な原因
- HDD/SSDの故障:
起動ドライブ(HDDやSSD)が物理故障や不良セクタだらけの状態になると、OSの読み込みに失敗して起動できません。
ロゴの後にエラー表示(「オペレーティングシステムが見つかりません」など)が出ることもありますが、症状によってはロゴ画面でフリーズすることもあります。 - メモリの不具合:
RAM(メモリ)が故障していたり、接触不良を起こしていると、起動途中でシステムが停止することがあります。
本来であればビープ音などでエラーを知らせるケースもありますが、軽微な不具合だとロゴ画面から進まない状態になる場合があります。 - マザーボードやCMOS電池の異常:
マザーボード上の部品劣化や故障、BIOSの設定情報を保持するCMOS電池切れなどにより、POST(電源投入時の自己診断)が正常に完了せず起動が止まるケースです。
特にCMOS電池が弱ると起動時に必要な情報を読み込めず、ロゴ画面で固まってしまうことがあります。 - 電源ユニットの問題:
デスクトップPCの場合、電源ユニットが劣化または故障して十分な電力を供給できないと、起動途中でシステムがフリーズしたり再起動を繰り返すことがあります。
電源が不安定だと一見ロゴまでは表示されるものの、その後先に進まない、といった症状につながります。
以上のように、多岐にわたる原因が考えられます。
原因を特定するのは難しい場合もありますが、自分でできる範囲で切り分けと対処を試みることが重要です。
次章からは、まずソフトウェア関連の解決策、続いてハードウェア関連の解決策を順に紹介します。
ソフトウェア関連の解決策
ソフトウェアが原因でパソコンが起動しない場合、適切な手順を踏むことで問題を解消できることがあります。
以下に、考えられるソフトウェア面での対処法を順番に説明します。
まずは強制再起動と周辺機器の取り外し
最初に試していただきたいのは、基本的なリセット措置です。
ロゴ画面でフリーズした場合、電源ボタンを長押しして一度強制終了してください。
完全に電源が切れたことを確認したら、プリンターや外付けHDD・USBメモリなど不要な周辺機器をすべて取り外します。
その後、再度電源を入れてみましょう。余計なデバイスが原因だった場合、これだけで正常起動できることがあります。
ノートパソコンの場合はACアダプターとバッテリーを一度外し、数十秒待ってから再接続して起動する「放電(パワードレイン)」も効果的です。
セーフモードでの起動を試す
通常起動ができない場合でも、セーフモードであれば起動できる可能性があります。
セーフモードとはWindowsを必要最小限の構成で起動するモードで、ドライバや常駐ソフトの影響を排除できます。
起動時にメーカーのロゴが表示されたらすぐにF8キーを何度も押してみてください
(機種によってはShift+F8やF11の場合もあります)。
うまくいけば「詳細ブートオプション」メニューが表示されるので、「セーフモード」を選択して起動します。
Windows 10/11では従来のF8キーが効かない場合もありますが、起動に失敗した状態を数回繰り返すと自動的に修復モードに入ります。
電源投入→ロゴで止まる→長押しで強制終了、を2~3回行うと、自動修復やセーフモード起動のメニューが表示されることがあります。
セーフモードで起動できた場合は、直近にインストールしたソフトウェアやドライバーのアンインストール、ウイルススキャン、不要なファイルの削除などを行ってみましょう。
その後再起動して通常起動が復旧するか確認します。
BIOS設定の確認とリセット
次に、BIOS設定をチェックしてみましょう。
起動直後にF2キーやDeleteキー(機種により異なる)を連打するとBIOSセットアップ画面に入れます。
BIOS画面では、まず起動ドライブが正しく認識されているか確認します。
HDD/SSDの型番が表示されていなかったり、
起動順序(Boot Priority)が別のデバイスになっている場合は、それが原因の可能性があります。
特に、USBメモリや光学ドライブが最優先になっていると、OSの入ったドライブより先にそれらを読みに行くため起動できません。
正しい起動ドライブ(通常は内蔵HDD/SSD)がファーストブートになっているか確認し、必要に応じて変更してください。
設定に自信がない場合は、BIOSセットアップ内の「Load Setup Defaults(デフォルト設定を読み込む)」または「最適化設定をロード」といった項目を選び、BIOS設定を初期状態にリセットするのも有効です。
その後設定を保存して再起動し、改善するか試します。
Windowsの修復オプションを実行
Windowsには起動トラブルを解決するための修復機能が備わっています。
ロゴから先に進まない状態が続く場合、自動的に「自動修復」画面が表示されることがあります。
その際は画面の指示に従って自動修復(スタートアップ修復)を実行してみてください。
自動修復がうまくいかない場合は、「詳細オプション」からさらに対処を試みます。
詳細オプションでは、まず「システムの復元」を試すことをおすすめします。
以前正常に動作していた時点の復元ポイントがあれば、その状態にシステムを戻すことで問題が解決する可能性があります。
ただし復元ポイントを作成していない場合は利用できません。
その場合は「設定の変更」や「アンインストール」オプションで、直近のWindowsアップデートを一時的に削除する方法もあります。
また、コマンドプロンプトを開いて
ブート構成の修復を行うことも可能です(上級者向け)。
具体的にはbootrec /fixmbrやbootrec /fixboot、bootrec /rebuildbcdといったコマンドを試すことで、
壊れたブートセクタを修復できる場合があります。
以上の修復オプションを試した後はPCを再起動し、正常にWindowsが立ち上がるか確認しましょう。
それでも状況が変わらない場合、次の手段としてOSの再インストールを検討します。
インストールメディアを使ったOSの再インストール
ソフトウェア面の最終手段は、Windows自体を再インストールすることです。
Windows 10/11の場合、別の正常なPCでWindowsのインストールメディア(USBメモリ)を作成し、
それを使って起動できないPCをブートします。
起動時にF12やEscキーでブートメニューを表示させ、USBメモリから起動してください。
セットアップが始まったら、「コンピューターを修復する」を選ぶことで先ほど述べた修復オプション(スタートアップ修復やシステムの復元等)にアクセスできます。
修復でも改善しない場合は、最終的にWindowsのクリーンインストールを行います。
ただしクリーンインストールを行うとデータやアプリケーションは初期化されてしまうため、
重要なデータのバックアップを事前に取れるなら取っておきましょう。
再インストールによってシステム面の問題は解決するはずですが、もし原因がハードウェアにあった場合は再インストール中にエラーが出たり、インストール完了後も同じ症状が発生する可能性があります。
その場合は次に説明するハードウェア面の点検が必要です。
ハードウェア関連の解決策
ソフトの問題ではない場合、ハードウェアに起因するトラブルを確認・対処していきます。
内部パーツの状態確認や交換作業になるため、無理のない範囲で進めましょう。
HDD/SSDの接続確認・交換
まずはストレージデバイス(HDD/SSD)をチェックします。
デスクトップPCの場合はサイドパネルを外し、HDDやSSDとマザーボードを繋ぐSATAケーブルおよび電源ケーブルがしっかり接続されているか確認してください。
ケーブルが緩んでいたり、腐食して接触不良になっていると正常にドライブを読み込めず起動できません。
ケーブルを一度抜き差ししたり、予備と交換してみるのも有効です。
ノートパソコンの場合はユーザー自身でHDD/SSDにアクセスできるモデルであれば、一旦取り外して再度装着し直してみます。
接触状態が改善されることがあります。
それでも認識しない場合や、HDDから異音がする場合はドライブ自体の故障が疑われます。
別の正常なPCに接続してデータが読み出せるか試したり、新しいドライブと交換してWindowsをインストールし直すことで
起動するか確認しましょう。
※データが大切な場合、故障したHDD/SSDからのデータ取り出しは高度な作業になるため、自分で無理に行わず専門業者に依頼することをおすすめします。
メモリのチェック(取り外し・再挿入、診断ツール)
次にメモリ(RAM)を点検します。
パソコン本体の電源を落とし、電源ケーブル(ノートPCならバッテリーも)を外してから、
本体内部のメモリモジュールを確認しましょう。
デスクトップPCではメモリスロットの両端の留め具を開放してモジュールを取り外し、
埃を飛ばしてからもう一度確実に差し直してみます。ノートPCでも可能であれば同様に行います。
メモリを複数枚搭載している場合は、1枚ずつに減らして起動を試すことで不良メモリの切り分けができます。
1枚で起動しなければ別の1枚に差し替えて確認してください。
どれか一枚でも起動すれば、その差し替えたメモリが故障している可能性が高いです。
また、BIOSやWindowsのメモリ診断ツールを使ってメモリテストを実行することも有効です。
Windowsのメモリ診断は、起動可能な場合は「Windowsメモリ診断」と検索して実行、
起動不可の場合でもインストールメディアからコマンドプロンプトを開きmdsched.exeを実行することでテストが可能です。
もしメモリの不良が判明した場合は、新しいメモリモジュールへの交換が必要です。
メモリはユーザー自身で比較的交換しやすい部品ですが、対応規格(DDR3/DDR4/DDR5など)や容量上限がありますので、
適合する製品を選ぶようにしましょう。
電源ユニットやマザーボードの確認(CMOSリセット・通電確認)
上記を試しても改善しない場合、電源ユニットやマザーボードといった主要部品の問題が考えられます。
まずデスクトップPCでは電源ユニットの通電状況を確認しましょう。電源ファンやCPUファンが回っているか、マザーボード上のLEDが点灯しているかなどをチェックします。
ロゴ画面までは表示される場合は完全に電源が死んでいるわけではありませんが、
必要な電圧が安定供給されていない可能性があります。電源ユニットの故障診断は専門機器がないと難しいため、予備の電源ユニットがあれば交換して状況が変わるか試す方法もあります。
マザーボードに関しては、自力でできることとしてCMOSクリア(リセット)があります。
PCをシャットダウンし、電源ケーブルを抜いた状態でマザーボード上のボタン電池(CMOS電池)を取り外します。
数分待ってから電池を元に戻し、再度PCを起動してみましょう。
これによりBIOS設定が初期化され、一時的な設定不具合が解消されることがあります。
また、マザーボード上のジャンパーピンでCMOSクリアを行う方法もあります(マニュアル参照)。
これでも症状が改善しない場合、マザーボードそのものの故障やその他のハードウェア不良が疑われます。
特定の部品を断定するのは難しく、この段階では無理に自力で解決しようとせず、
専門の修理業者に診断を依頼することを検討してください。
修理が必要な場合の対処法
上記の対策を試してもなおパソコンがメーカーロゴから進まない場合や、そもそも分解などの作業が難しい場合は修理専門店に相談をするのが確実です。
ここでは、自分で対応できるケースと専門業者に依頼すべきケースについて整理します。
- ソフトウェアに起因する問題で、自分でOSの再インストールまで試したが直らない場合
- データ復旧が絡む問題(故障したHDDからデータを取り出したい等)は無理をせず専門家へ
- 明らかにハードウェアの故障(異臭がする、焦げ跡がある、コンデンサ破裂など)が見られる場合
- 分解や部品交換に自信がない、工具がない場合
上記に当てはまるときは、早めに修理業者へ相談しましょう。
当社は起動トラブルを含む様々なパソコン修理に対応していますが、お問い合わせフォームやお電話からお気軽にご相談いただけます。
お問い合わせやお見積もりは無料ですので、
「修理費用がどれくらいかかるか知りたい」「どんな修理内容になるのか聞いてみたい」という段階でも遠慮なくご連絡ください。
修理依頼の際は、症状(「メーカーのロゴから進まない」状態であること)やこれまで試した対処法について伝えるとスムーズです。
PC本舗では全国対応の宅配修理サービスを行っており、宅配便でパソコンを送っていただければ詳しい診断の上、修理内容と正式なお見積もりをご提示します。
事前に了承いただかない限り勝手に修理を進めることはありませんので安心です。
修理の流れや料金の目安については当サイト内の「修理の流れ」や「料金表」ページでもご確認いただけます。
まとめと次のステップ
パソコンがメーカーのロゴから進まないときは焦ってしまいますが、原因はソフトウェア・ハードウェア含めて様々です。
本記事で解説したように、まずは簡単な対処法から順に試すことが大切です。
- 強制再起動と周辺機器の取り外し、放電の実施
- セーフモードでの起動やBIOS設定の確認
- 自動修復やシステムの復元などWindowsの修復機能の活用
- 必要に応じたOS再インストール
- HDD/SSD・メモリなどハードウェアの接続チェックと交換テスト
- CMOSリセットなどマザーボード・電源周りの対処
これらの手順で改善するケースも多くあります。
特にWindowsアップデートが原因の場合は、修復オプションで比較的容易に直ることもありますし、
ケーブルの緩みなど単純な理由であれば接続し直すだけで解決することもあります。
それでも状況が改善しない場合は、無理をせずプロの手に委ねるのが最適です。
放置しておくとデータ損失が深刻化したり、他の部分にも不具合が波及する可能性もあります。
「もうお手上げだ」というときは、ぜひPC本舗の問い合わせフォームからご相談ください。
専門のスタッフが原因を特定し、適切な修理プランをご提案いたします。
大切なパソコンを長く使い続けるためにも、早めの対処と必要に応じたプロへの相談で、不具合を解消して安心を取り戻しましょう。